無機物の中でも最もホットな材料の一つがグラフェンでしょう。
いうまでもないですが、グラフェン(graphene)は、2005年にNovoselovとGeim(と他の人)が、Natureに発表し、2010年には二人にノーベル賞が出たという、物質です。
その構造はベンゼン環が多数縮環した単層膜で、炭素の同素体であり、鉛筆の文字にも含まれている(といっていいと思われる)
"Simple is the best"
を体現したような材料です。
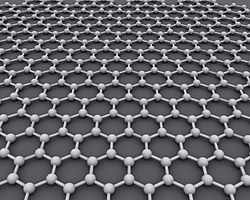
その単純な構造は、物理学者だけでなく、電気・電子、
果ては数学者や生物系をも巻き込むムーブメントになっていると言えるでしょう。
しかし化学者、特に有機系のみなさまにとっては、ツルツルしていてイマイチつかみ所がない、という感覚ではないでしょうか。
それともフラーレンをあんなのや、こんなのにする有機の皆様ですから、グラフェンなど屁でもない、という感覚なのでしょうか。
Grapheneを化学的に扱う、という仕事も多数あり、例えば超分子的な相互作用を用いて溶媒に分散させる、というようなテーマもホットです。
|
グラフェン |
酸化グラフェン |
|
炭素のみ |
炭素と酸素と水素もいっぱい |
|
SP2混成軌道 |
SP3混成軌道 |
|
完全な平面 |
グニャグニャしている上に欠陥もたくさん |
|
電気を流す(半金属的?) |
電気は流さない |
|
疎水的で水に分散しない |
親水的で水に分散する |































