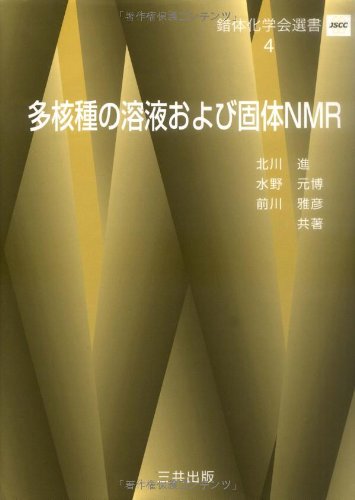北川 進(きたがわ すすむ、1951年7月4日-)は、日本の無機化学者である (写真:https://kuias.kyoto-u.ac.jp/)。京都大学 高等研究院 特別教授。2025年ノーベル化学賞受賞。
経歴
1974 京都大学 工学部 石油化学科 卒業
1979 京都大学大学院 博士号取得
1979 近畿大学 助手
1983 近畿大学 講師
1986 テキサス大学オースティン 客員研究員 (F.A.Cotton教授)
1988 近畿大学 助教授
1992 東京都立大学 教授
1998 京都大学大学院工学系研究科 教授
2007 京都大学物質-細胞統合システム拠点・副拠点長(兼任)
2007-2013 ERATO『北川統合細孔プロジェクト』リーダー(兼任)
2013 京都大学物質-細胞統合システム拠点・拠点長(兼任)
2017 京都大学 高等研究院 特別教授
2017 京都大学 高等研究院 物質-細胞統合システム拠点 拠点長
2020 京都大学 高等研究院 副院長
2024 京都大学 理事・副学長(研究推進担当)
受賞歴
1990 日本化学会若手講演賞
2002 第19回日本化学会学術賞
2007 錯体化学会賞
2008 フンボルト賞
2009 第61回日本化学会賞
2010 トムソン・ロイター引用栄誉賞
2011 文部科学大臣表彰科学技術賞研究部門
2011 紫綬褒章
2011 京都新聞大賞文化学術賞
2013 平成25年度京都大学孜孜賞
2013 第10回江崎玲於奈賞
2013 The RSC de Gennes Prize
2014 Thomson Reuters Highly Cited Researcher
2015 マルコ・ポーロ イタリア科学賞
2016 日本学士院賞
2016 Thomson Reuters Highly Cited Researcher
2017 the Future Solvay Prize
2017 藤原賞
2017 ソルベイ未来化学賞
2017 日本化学会名誉会員
2018 フランス化学会グランプリ
2019 エマニュエル・メルク レクチャーシップ賞
2019 日本学士院会員
2021 錯体化学会名誉会員
2023 英国王立協会外国人会員
2025 京都府文化賞特別功労賞
2025 ノーベル化学賞
研究概要
配位性高分子錯体を用いる新規材料創製と空間機能開拓
多孔性配位性高分子(PCP)もしくは金属有機構造体(MOF)と呼ばれる化合物は有機物と無機物のハイブリッドたる多孔性材料である。
軽量で高い比表面積を実現することが出来、とりわけ水素やメタンなどのエネルギー観点から重要なガスを貯蔵できる材料としての応用が期待されている。
《画像:http://www.spring8.or.jp/》
コメント&その他
- 研究者を志したきっかけは「化学者はエタノールとメタノールの違いを理解できるから」。
- 趣味は探偵もの、警察フィクションノベル、歌舞伎とスーパー歌舞伎、ヨーロッパのスリラー映画
- ノーベル化学賞受賞の電話連絡の際、「最近、変な勧誘の電話がよく掛かってくるのでまたかと思って疑って不機嫌に取ったら、スウェディッシュアカデミーの選考委員長と名乗られた」とのこと。
名言集
『ただやみくもに新しいものを作るのではなく、コンセプトを考え、ビジョンを示し、先を予測する。そこから真の飛躍が始まるのです。これぞ研究の醍醐味だと私は思っています。』
『しぶとく粘る。いろんな経験をする。そうすれば、きっと「ダイヤモンドの鉱石」がすぐそばにあることに気がつくことができると思います。』
※いずれも enago 「高被引用論文著者(HCR)インタビュー (2019)」より
関連動画
https://www.youtube.com/watch?v=pEQhU2J9BIE
関連文献
- Kitagawa, S.; Kitaura, R.; Noro, S. I. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 2334. DOI: 10.1002/anie.200300610
- R. Matsuda, R. Kitaura, S. Kitagawa, Y. Kubota, R. V. Belosludov, T. C. Kobayashi, H. Sakamoto, T. Chiba, M. Takata, Y. Kawazoe, Y. Mita, Highly controlled acetylene accommodation in a metal–organic microporous material. Nature 436, 238–241 (2005).
- Y. Sakata, S. Furukawa, M. Kondo, K. Hirai, N. Horike, Y. Takashima, H. Uehara, N. Louvain, M. Meilikhov, T. Tsuruoka, S. Isoda, W. Kosaka, O. Sakata, S. Kitagawa, Shape-memory nanopores induced in coordination frameworks by crystal downsizing. Science 339, 193–196 (2013).
- H. Sato, W. Kosaka, R. Matsuda, A. Hori, Y. Hijikata, R. V. Belosludov, S. Sakaki, M. Takata, S. Kitagawa, Self–Accelerating CO Sorption in a Soft Nanoporous Crystal. Science 343, 167–170 (2014).
- N. Hosono, A. Terashima, S. Kusaka, R. Matsuda, S. Kitagawa, Highly responsive nature of porous coordination polymer surfaces imaged by in situ atomic force microscopy. Nature Chemistry 11, 109–116 (2018).
- C. Gu, N. Hosono, J. Zheng, Y. Sato, S. Kusaka, S. Sakaki, S. Kitagawa, Design and control of gas diffusion process in a nanoporous soft crystal. Science 363, 387–391 (2019).
関連書籍
集積型金属錯体: クリスタルエンジニアリングからフロンティアオービタルエンジニアリングへ
チャンピオンレコードをもつ金属錯体最前線: 新しい機能性錯体の構築に向けて (化学フロンティア 16)