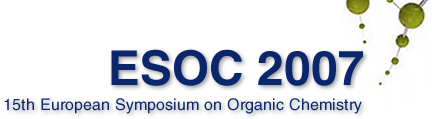bergです。この度は2024年7月3日(水)にオンラインにて開催された、自然科学研究機構 分子科学研究所の第139回分子科学フォーラム「どこが特別!?ペロブスカイト太陽電池の性能と社会実装の可能性とは?」を聴講してきました。この記事では会の模様を簡単に振り返ってみたいと思います。
演題と概要は以下の通りです。
演者: 宮坂 力 特任教授(桐蔭横浜大学)
題目: どこが特別!?ペロブスカイト太陽電池の性能と社会実装の可能性とは?
場所: オンライン(Youtubeライブ)
主催: 自然科学研究機構 分子科学研究所
共催: 公益財団法人 豊田理化学研究所
日時: 2024年7月03日(水) 18:00 より 19:30
詳細:シリコン結晶太陽電池の最高効率に届いたペロブスカイト太陽電池の特徴と製造技術、そして産業実装に向けた軽量フレキシブルなモジュールの開発を紹介し、これまでの太陽電池とどこが違い、どこが優れているのか、どのような使い方が可能になるのかを解説します。
https://www.ims.ac.jp/research/seminar/2024/03/22_6240.html
アーカイブ配信:
※録画・録音はご遠慮ください。
宮坂先生は 2009年のJACS誌の被引用数が約2万、2012年のScience誌が約1.1万と、一般にノーベル賞級の水準とされる数千をはるかにしのいでいるほか、2009年にGHC(グリーンサステナブルケミストリー)文部科学大臣賞、2017年に日本化学会賞、2019年に応用物理学会業績賞、2020年に山崎貞一賞、市村学術賞(功績賞)、2021年は英国ランク財団 光エレクトロニクス部門、2024年には朝日賞を受賞されるなど、数々の錚々たる褒章を総なめされています。
ご存じの通り、ペロブスカイトとは、ABX3(A:カチオン、B:Pb(II)・Sn(II)などの2価の金属、X:ヨウ素などのハロゲン化物イオン)型の複塩における八面体型の結晶構造を指します。Xに酸化物の代わりにハロゲン化物を用いることで極性溶媒への溶解性を向上させることができ、スピンコートにより溶液を塗布することで常温で容易に製膜・自己組織化させられるほか、AにはCH3NH3+やHC(NH2)2+などの有機塩基を導入することも可能で、吸収波長のチューニングも可能です。
ペロブスカイト太陽電池の発見についてのお話として、宮坂先生が設立された、Peccellという色素増感太陽電池を主に研究していた会社に所属していた学生が発端であったこと、既に結晶シリコン太陽電池に迫る26%台の光電変換効率が達成されていること、透明性の高い製品を作ることができ、ガラス窓など建材としても利用可能であること、出力電圧が高く熱損失が極めて小さいこと、カリウムイオンをドープすることで結晶粒界を減らすことができ、効率が向上することなど、非常に印象に残りました。
また、ペロブスカイト太陽電池は現在、すでに理論限界ぎりぎりまで性能が向上していますが、さらなる結晶粒界のパッシベーションにカフェインが使われること、オール無機ペロブスカイトでも効率を維持でき、耐熱性も向上できること、軽量・フレキシブルで屋内光での効率が高いためにウェアラブルデバイスへの応用が期待できることなど、太陽光発電の概念を一新するブレイクスルーであることが強く実感できました。
さらに、成膜に必要な印刷技術や世界的には希少な資源である要素の埋蔵量など、この分野で日本は高い優位性を誇っており、非常に高いポテンシャルのある産業であることなども力説されており、非常に夢の感じられるおはなしでした。
民間企業に就職して以来このような最先端の研究に触れる機会がめっきり減ってしまっていたので、今回の講演会は非常に刺激的で新鮮で、あっという間の90分でした。最後になりましたが、講演をセッティングしてくださった分子科学研究所の関係者各位、そして、長きにわたりご講演くださった宮坂先生に心よりお礼申し上げます。今後の研究の進展も楽しみにしています。