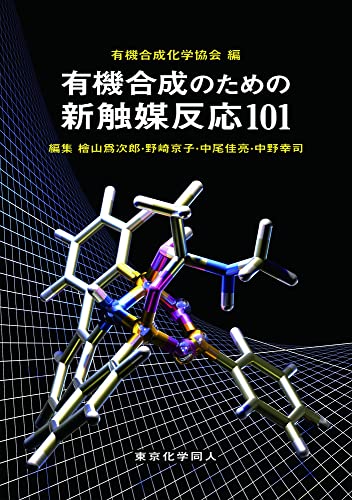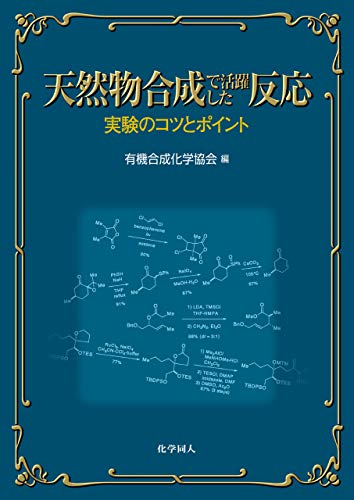第 360回のスポットライトリサーチは、広島大学大学院 先進理工系科学研究科 博士課程後期 1年次の 対馬 拓海 (つしま・たくみ) さんにお願いしました。対馬さんの所属する有機典型元素化学研究室 (吉田 拡人 教授) は 2020 年 4 月に発足したばかりのフレッシュな研究室で、まだ見ぬ反応や分子の創成を目指した最先端の有機化学研究を行なっています。その研究手法の一つに「ホウ素のルイス酸性を抑制する」という独特なアプローチがあり、これまでに類のない化学選択性や反応性を示す新規ホウ素化反応を多数開発されています。対馬さんは「ホウ素のルイス酸性抑制」と「配位子の立体的嵩高さ」を鍵に、鈴木-宮浦クロスカップリング反応に利用可能なホウ素部位を、末端アルキンの内部炭素に導入することに成功しました。さらに開発した反応を用いて、抗腫瘍活性天然物の短工程全合成を達成し、それらの成果を ACS Catalysis 誌に発表しました。
Origins of Internal Regioselectivity in Copper-Catalyzed Borylation of Terminal Alkynes
Takumi Tsushima, Hideya Tanaka, Kazuki Nakanishi, Masaaki Nakamoto, and Hiroto Yoshida, ACS Catalysis, 2021, 11, 14381–14387, DOI: 10.1021/acscatal.1c04244
Abstract
Installation of a boron functionality into a more substituted carbon of terminal alkynes has been a challenging issue in chemical synthesis, since inherently Lewis acidic boron moieties, in principle, favor their attachment to a terminal carbon. Herein, we report on the highly internal-selective borylation of terminal alkynes under copper catalysis, wherein diminishment of boron-Lewis acidity and ligand-derived steric bulk around a copper center are the key to the success. In particular, the use of an anthranilamide-substituted boron moiety [B(aam)] is of high synthetic significance, because its properly diminished Lewis acidity enabled the internal regioselectivity and the Suzuki–Miyaura cross-coupling activity to be compatibly achieved. This method provided a direct and universal approach to variously substituted branched alkenylboron compounds, regardless of electronic and steric properties of a substituent on terminal alkynes.
プレスリリースはコチラ。
広島大学大学院先進理工系科学研究科の吉田拡人教授を中心とした研究チームは、「銅触媒を用いた末端アルキンの内部選択的ヒドロホウ素化反応」の内部選択性発現の鍵は「ホウ素のルイス酸性抑制」と「配位子の立体的嵩高さ」であることを明らかにしました。これに基づき、「適度にルイス酸性を抑制したホウ素部位」と「立体的に嵩高い配位子を持つ銅触媒」を組み合わせることにより、「ヒドロホウ素化反応の完全な内部選択性」と「温和な条件での SMC 反応」を両立することに成功しました。従来、ホウ素導入反応の一般則である逆マルコフニコフ則を覆し選択性を逆転させるためは、強力にルイス酸性を抑制したホウ素部位を用いることが不可欠でした。一方で強力にルイス酸性を抑制したホウ素部位を SMC 反応に用いることは困難でした。本反応は、ホウ素のルイス酸性に起因する内部選択性と SMC 活性のジレンマを解決する画期的な研究といえます。本研究成果は、今後の新しいホウ素導入反応の指針となることはもちろん、多段階を必要とした種々有用分子合成の短工程化にも貢献することが期待されます。
本研究成果は、米国化学会 「ACS Catalysis」 オンライン版に 11 月 15 日に掲載されました。
また対馬さんは本研究の成果に関連して 2021年の第 67 回有機金属化学討論会にて発表を行い、みごとポスター賞を受賞されています (吉田研HPより)
研究室を主宰されている吉田 拡人 先生より、対馬さんの人柄についてのコメントを頂いております。
対馬君は、修士課程修了後いったん就職しましたが、2年後に博士取得を強く志し、研究室に戻ってきてくれました。人生における大きな決断に違わず、文字どおり研究に熱中しています。今回の研究は、対馬君が彼の強みである、根気強さ・実験の丁寧さ・鋭い観察力を存分に活かして、大部分を1人で成し遂げました。新しい技術を取り入れることにも意欲的で、今後は研究室に新しい風を吹き込んでくれるとともに、学生のリーダーとして研究室を牽引してくれると期待しています。
末端オレフィンを効率的に合成可能な本手法は、鈴木–宮浦クロスカップリングに続く溝呂木–Heck 反応も可能であると考えられ、天然物の骨格構築に留まらず、医薬品ヒット化合物の構造展開など様々な分野で応用されうる画期的な反応だと思います!
それでは、インタビューをお楽しみください!
【Q1. 今回プレスリリースとなったのはどんな研究ですか?簡単にご説明ください】

我々の研究グループでは、適度にルイス酸性が抑制されたホウ素部位 [B(aam)] を末端アルキンの内部炭素に導入する「銅触媒を用いた末端アルキンの内部選択的ヒドロホウ素化反応」を開発しました(図1)。本手法により末端アルキンに導入された B(aam) 部位は弱塩基性条件下、ワンポットで鈴木-宮浦クロスカップリング (SMC) 反応に利用可能であり、生物活性分子 iso-Combretastatin A4 の短工程全合成を達成しました(図2)。

従来、ホウ素導入反応の一般則である anti-Markovnikov 則を覆し、内部炭素にホウ素を導入するには、強力にルイス酸性を抑制したホウ素部位 [B(dan)] を用いることが不可欠でした[1]。一方で B(dan) 部位を直接 SMC 反応に適用するには、強力なルイス酸性抑制効果に打ち勝つ tert-BuOK や Ba(OH)2 のような強塩基を用いることが必須です[2]。本反応は、ホウ素のルイス酸性に起因する内部選択性と SMC 活性のジレンマを解決する画期的な研究といえます。
また、本研究ではホウ素のルイス酸性を理論計算により数値化する FIA (Fluoride Ion Affinity) の値と配位子の立体的嵩高さを表す %Vbur (Percent Buried Volume) の値が内部選択性と相関することから、「ホウ素のルイス酸性抑制」と「配位子の立体的嵩高さ」が内部選択性発現の鍵であることを明らかにしました。
本研究成果は、今後の新しいホウ素導入反応の指針となることはもちろん、多段階を必要とした種々有用分子合成の短工程化にも貢献することが期待されます。
【Q2. 本研究テーマについて、自分なりに工夫したところ、思い入れがあるところを教えてください】
直鎖型ホウ素置換アルケンの生成を抑制し、分岐型ホウ素置換アルケンのみを得るため、膨大な量の条件検討を行いました。どのような条件でも直鎖型ホウ素置換アルケンが検出されたため、「選択性を制御できないのではないか」と諦めたくなる苦しい時期もありましたが、データを積み重ねることで、銅触媒が極めて重要であることが判明しました。そして、配位子の立体的嵩高さを示す %Vbur を活用しながら、銅触媒の検討を集中的に進めたところ、%Vbur の値が大きな (立体的に嵩高い配位子を持つ) 銅触媒を用いることで、内部選択性を完全に制御することに成功しました(図3)。GC や NMR で分岐型ホウ素置換アルケンのみのピークを確認した時の興奮は今でも覚えています。

【Q3. 研究テーマの難しかったところはどこですか?またそれをどのように乗り越えましたか?】
%Vbur や FIA を研究に取り入れることが難しかったです。当初、所属する研究室では、%Vbur を活用していなかったため、銅触媒の単結晶X線構造解析や %Vbur を算出する WebTool(SambVca 2.1)の使用方法などを習得するところからのスタートでした。単結晶X線構造解析に精通している方に技術指導していただきながら、%Vbur を取り扱う論文を参考にすることで、%Vbur を算出する方法を習得しました。FIA の活用も同様の苦労がありましたが、ホウ素のルイス酸性を直感ではなく数値化して評価できるようになったことで、反応性の議論がより深まりました (図4)。

【Q4. 将来は化学とどう関わっていきたいですか?】
私は小学生のころから化学実験が好きで、今でも変わりません。これからも実験ができる環境で研究を続けることで、化学と関わりを持つことを望んでいます。
今後も研究を続けていくために、研究者は常に視野を広くする必要があると考えています。この考えは一度、企業での研究を経験したことで、より一層強くなりました。今回の研究で %Vbur や FIA を取り入れたように、今後も新しいことにアンテナを張り、有用な技術や考え方 (プログラミングや統計学など) を習得しながら研究を続ける予定です。将来的には様々なアプローチで研究を進めることができる研究者になり、化学の発展に貢献していきたいと考えています。
【Q5. 最後に、読者の皆さんにメッセージをお願いします】
今回プレスリリースしていただいた研究は私が学部4年生の頃から続けていた研究です。苦労してデータを積み重ねてやっと論文化することができました。ここまで長期間、根気強く取り組めた要因には、「研究が面白い」と心から思って取り組めていたことが大きいと思っています。仮説通りに進行しない実験に対しても「なんでだろう。何が起こっているんだろう。面白いなぁ」と思うことが実験姿勢として大切だと思います。どんな実験結果に対しても面白がりましょう。
【研究者の略歴】

パン屋巡りが趣味です。
名前:対馬 拓海
所属:広島大学大学院先進理工系科学研究科 有機典型元素化学研究室 博士課程後期1年
研究テーマ:
「銅触媒を用いた末端アルキンの内部選択的ヒドロホウ素化反応」
「銅触媒を用いた末端アルキンの内部選択的カルボホウ素化反応」
経歴
2017年3月 広島大学(工学部 第三類 応用化学課程) 卒業
2019年3月 広島大学大学院(工学部研究科 応用化学専攻) 修士課程修了
2019年4月―2021年3月 渡辺化学工業株式会社 研究開発部所属
2021年4月―2021年9月 広島大学大学院(先進理工系科学研究科) 研究生
2021年10月―現在 広島大学大学院(先進理工系科学研究科) 博士課程後期
積極的に計算化学を導入し、緻密に反応の鍵を解き明かした素晴らしい研究でした!
対馬さん、吉田先生、インタビューにご協力いただきありがとうございました!
それでは、次回のスポットライトリサーチもお楽しみに!
参考文献
[1] Yoshida, H.; Takemoto, Y.; Takaki, K. “A masked diboron in Cu-catalysed borylation reaction: highly regioselective formal hydroboration of alkynes for synthesis of branched alkenylborons”, Chem. Commun, 2014, 50, 8299−8302. DOI: 10.1039/C5CC00439J
[2] (a) Yoshida, H.; Seki, M.; Kamio, S.; Tanaka, H.; Izumi, Y.; Li, J.; Osaka, I.; Abe, M.; Andoh, H.; Yajima, T.; Tani, T.; Tsuchimoto, T. “Direct Suzuki−Miyaura coupling with naphthalene-1,8-diaminato (dan)-substituted organoborons“, ACS Catal, 2020, 10, 346−351. DOI: 10.1021/acscatal.9b03666, (b) Mutoh, Y.; Yamamoto, K.; Saito, S. “Suzuki−Miyaura cross-coupling of 1,8-diaminonaphthalene (dan)-protected arylboronic acids”, ACS Catal, 2020, 10, 352−357. DOI: 10.1021/acscatal.9b03667