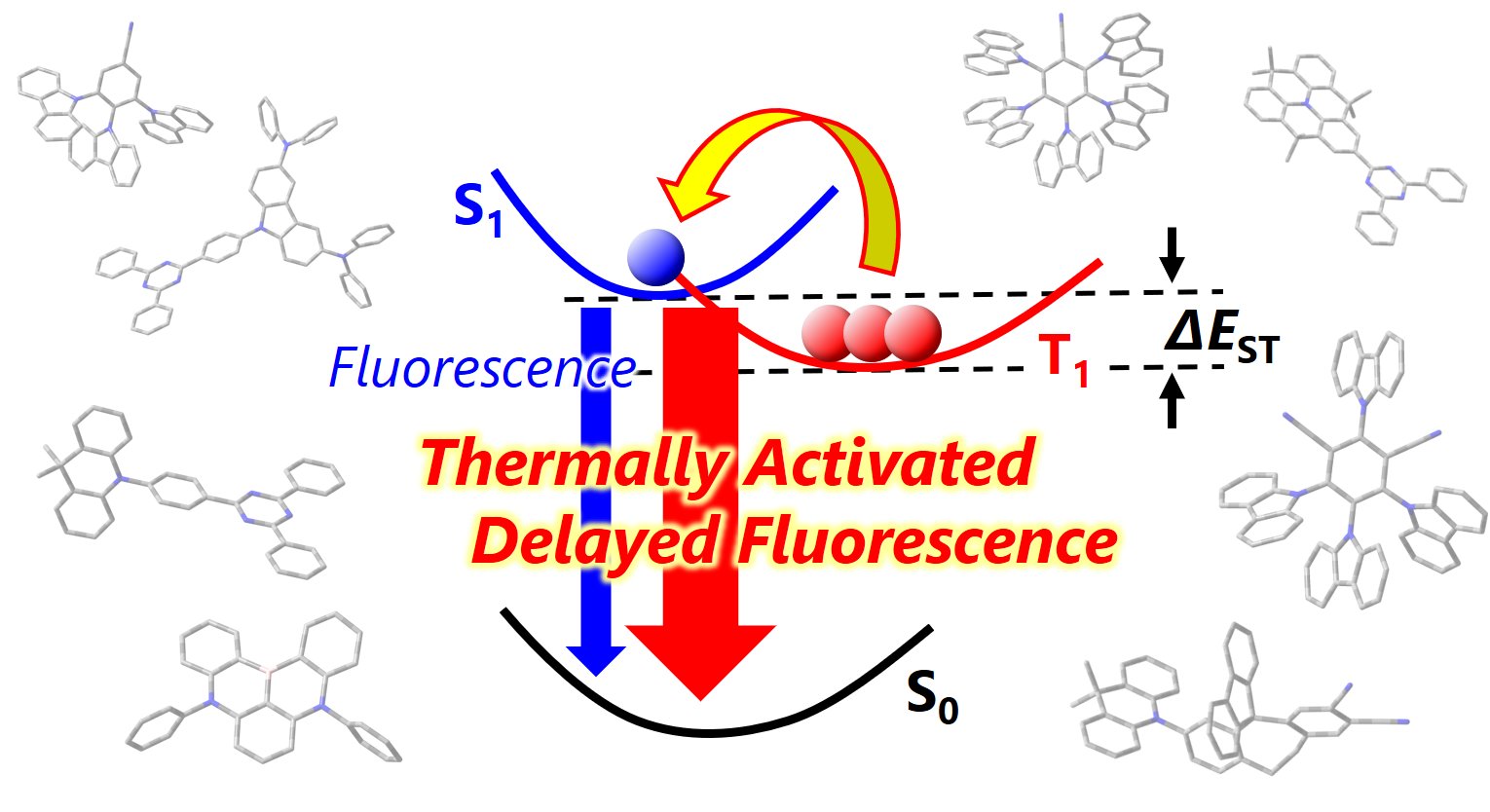フェン・チャン(Feng Zhang, 1982年xx月xx日(中国生)-)は、アメリカの生化学者、脳神経科学者である。マサチューセッツ工科大学、ブロード研究所、McGovern研究所 助教授。(写真:McGovern Institute)
経歴
2004 ハーバード大学 卒業(Ziaowei Zhuang教授)
2009 スタンフォード大学 博士号取得(Karl Deisseroth教授)
2011- マサチューセッツ工科大学 助教授
2011- ブロード研究所
2011- McGovern研究所
2018- マサチューセッツ工科大学 教授
Editas Medicine社 Founder。
受賞歴
2018 Keio Prize
2018 Vilcek Prize for Creative Promise
2017 Lemelson-MIT Prize
2017 Albany Prize
2017 Blavatnik Award for Young Scientists
2015 Tsuneko & Reiji Okazaki Award
2016 Canada Gairdner International Award
2016 トムソンロイター引用栄誉賞
2014 Alan T. Waterman Award
2014 Jacob Heskel Gabbay Award in Biotechnology and Medicine
2013 MIT Technology Reviews’s TR3
2012 Perl-UNC Neuroscience Prize
研究概要
光遺伝学技術の開拓
Karl Disseroth研在籍時に、光感受性を有する古細菌型ロドプシンタンパクを神経細胞に導入することで、その挙動をミリ秒単位で光制御できることをEd Boydenと共同で示した[1]。この発明により、現在の光遺伝学(Optogenetics)研究[2]の爆発的普及のきっかけを作った。
ゲノム編集技術の開発
ゲノム編集技術CRISPR/Cas9を開発。Emamnauelle CharpentierとJennifer Doudnaの共同グループが2012年に本技術をScience誌に報告した一方、技術特許はZhangに与えられた。本件は現在も特許先取権を巡り係争中である。
その後、CharpentierおよびDoudnaが哺乳類細胞に用いた系を最適化することで、世界で初めてヒト細胞への適用可能性を実証した[3,4]。
2015年には、CRISPR/Cas9系より簡便にゲノム編集を行える可能性のある技術として、CRISPR/Cpf1系を開発した[5]。

画像はこちらより引用
関連動画
関連文献
- “Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity” Boyden, E. S. ; Zhang, F.; Bamberg, E.; Nagel, G.; Deisseroth, K. Nature Neurosci. 2005, 8, 1263. doi:10.1038/nn1525
- “Method of the Year 2010”. Nature Methods 2010, 8, 1. doi:10.1038/nmeth.f.321
- “Multiplex Genome Engineering Using CRISPR/Cas Systems” Cong, L.; Ran, F. A.; Cox, D.; Lin, S.; Barretto, R.; Habib, N.; Hsu, P. D.; Wu, X.; Jiang, W.; Marraffini, L. A.; Zhang, F. Science 2013, 339,819. doi:10.1126/science.1231143
- “DNA targeting specificity of RNA-guided Cas9 nucleases” Hsu, P. D.; Scott, D. A.; Weinstein, J. A.; Ran, F. A.; Konermann, S.; Agarwala, V.; Li, Y.; Fine, E. J.; Wu, X.; Shalem, O.; Cradick, T. J.; Marraffini, L. A.; Bao, G.; Zhang, F. Nature Biotechnol. 2013, 31, 827. doi:10.1038/nbt.2647
- “Cpf1 Is a Single RNA-Guided Endonuclease of a Class 2 CRISPR-Cas System” Zetsche, B.; Gootenberg, J. S.; Abudayyeh, O. O.; Slaymaker, I. M.; Makarova, K. S.; Essletzbichler, P.; Volz,S. E.; Joung, J.; van der Oost, J.; Regev, A.; Koonin, E. V.; Zhang, F. Cell 2015, 163, 739. DOI: 10.1016/j.cell.2015.09.038