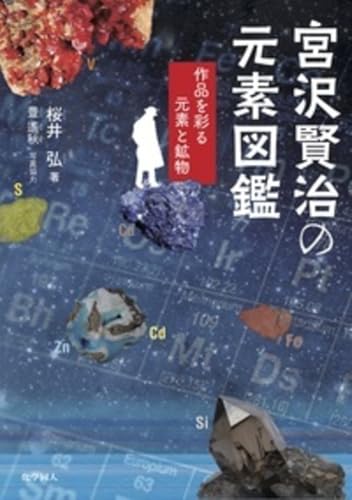2022年も折り返しに差し掛かりました。2022年は皆さんにとってどんな年になりそうですか。
ところで、2022年は何の年かご存知でしょうか。そう、2022年は五黄の寅であり、国際ガラス年でもあり、そして世界鉱物年です。
ユネスコにより2022年は世界鉱物年に制定されています。
そこで今回は、我々の生活に欠かせなくなっているハイテク材料が、鉱物の状態からどのように我々のもとにもたらされるか、すなわち、元素がふるさから我々のもとに来るまでの旅路を知ることができる書籍を紹介します。
概要
金属ってどこからきたの?
さあ元素のふるさとをたずねる旅に出よう!本書では、元素のふるさとである鉱山から金属元素(メタル)を取り出し、素材として役立つまでの道のりを図や写真を用いて紹介しています。
~中略~
こうした一連の流れを知ることで、元素が身近な製品に使われるまでの道のりは、科学技術だけでなく資源経済学や地政学にもつながることを実感できるでしょう。(化学同人 元素のふるさと図鑑より)
対象者
- 無機材料化学に興味のある方
- 多種の金属元素を扱う研究に興味のある方
- 資源を扱う商社マン、メーカーのビジネスマン
- 投資家
- 資源経済学・地政学に興味のある方
目次
メタルの元素周期表 / 本書に登場するおもな鉱山および地名 / 本書の使い方
第1章 地球の成り立ちと鉱石
第二章 功績が素材になるまで
第3章 生活と産業を作り出す元素 —ベースメタルが素材になるまで—
第4章 ハイテクを支える元素 —レアメタルが素材になるまで—
第5章 元素資源の未来 —深海底での開発は進むか—
付録 役に立つ用語集
解説
1章では、金属元素の生産量と価格の関係から、それぞれの金属元素がかかわる産業の大きさについて解説されています。金属資源の枯渇の目安となる耐用年数などの説明が記載されています。
2章では、掘り出された鉱石が素材になるまでの流れと、その周辺で起こっている問題が解説されています。鉱山で鉱石がどのような工程を経て精鉱になるのか、精錬所で行われている作業や副産物としてでてくるメタルの回収方法についても一連の流れがわかるよう図とともに丁寧に説明されています。また、廃棄物の処理法や過去に起こった資源危機の事例などの記載されています。
3章では現代社会に欠かせない道路や電線、ダム、鉄道といった社会基盤をつくる基礎的な構造材料として大量に生産、使用されている5つのベースメタル(鉄、アルミニウム、銅、亜鉛)に焦点を当てています。銅を例にして、鉱石からメタルを取り出して私たちが使う素材になるまでの道のりが具体的に解説されています。
4章ではスマートフォンなどのハイテク機器に不可欠なレアメタルについて、鉱石がメタルになるまでの流れ、埋蔵量や生産量、価格などの基礎データをその性質や用途とともに解説されています。
5章では、未来の資源開発に向けて行われている、未探査地域の探索や海洋資源開発における挑戦などについて解説されています。
感想
きれいな鉱石の写真はもちろん、採掘場所の写真や精錬時の説明図が多く掲載されており、元素が鉱山から我々の手元に届くまでの旅路を追体験するような感覚で理解できました。採掘から精錬までの説明も丁寧に記載されています。
(元素のふるさと図鑑より)
本書を読んで最も強く感じたことは、金属資源を材料に変えるまでの工程では非常に多くの手間がかかっているということです。
例えば、銅は現在の主要鉱山でも品位(鉱石中の目的金属の含有率)は0.4~0.5%であり、年間100万トンの銅を生産している鉱山では、その200倍の2億トン以上を採掘していることになります。一日当たりにすると、55万トン(街を走る10トントラック 55,000台分!!!)が採掘されています。さらに選鉱・精錬の過程で1.9億トン以上の沈積物が排出され、これを処理する必要があります。
当然鉱石を運搬する際にはエネルギーが必要ですし、精錬の際にもエネルギーを要します。アルミニウムの場合は精錬の際に多くの電力を消費し、鉄を鉱石から還元して得るためには大量のコークスを使用するため、地球温暖化ガスも排出されます。
すなわち、我々は金属資源の恩恵だけを享受しているのではなく、その裏では多くのエネルギーが消費され、地球温暖化を加速させていることにもなります。
ハイテク機器を使用するということは、その材料となる鉱物資源を得るためのエネルギー消費や地球温暖化ガスの排出に対して、消費者である我々にも責任が伴うことを意味しています。
本書を読むことで、ただ単にスマートフォンやパソコンなどのハイテク機器の恩恵を享受するだけではなく、それらの製品の消費者である我々も、原料となる鉱物資源の消費・開発について考え、見つめなおすきっかけになってほしいと思います。
おまけ
「元素のふるさと図鑑」刊行記念として、鉱物がおまけとしてプレゼントされます。(鉱石がなくなり次第終了・詳細は本書帯を参照)
私は黄銅鉱(CuFeSx)を頂きました。その輝きに照らされ、鉱物は生きている地球が生み出す「恵み」なのだと改めて実感しました。
そんな「恵み」が、世界の人々に格差なく享受される未来の実現を目指し、日々研究に取り組んでいこうと思います。

関連リンク
- 化学同人 元素のふるさと図鑑
- 化学工業日報 メタルの基礎知識にこの一冊
- ビジネスブックマラソン 『元素のふるさと図鑑』
- 日本は、銅と亜鉛の枯渇の危機に対応する必要があるでしょう。『元素のふるさと図鑑』
- 世界鉱物年