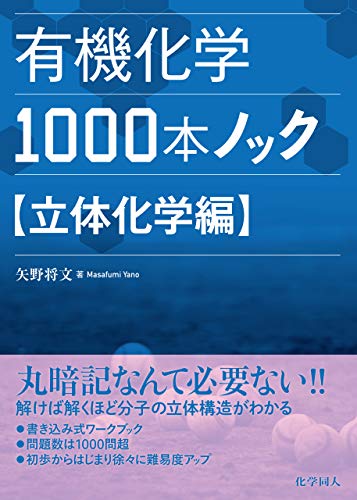概要
大学の有機化学では,反応の最初と最後だけ覚えるのではなく,その途中の過程を一つ一つていねいに追いかけることが求められる.反応は結合の切断と生成の繰り返しであり,どれだけ分子構造や反応が複雑になっても,電子の移動(曲がった矢印)が正しくわかっていれば怖れることはない.『命名法編』,『立体化学編』と同様に1000問超の問題を掲載.電子の移動が「身体に染みつく」まで解いて解いて解きまくれ!(引用:化学同人)
対象者
- 有機化学初学者
- 大学生
- 電子の移動についていけなくなった人
内容
この書籍は、以前も紹介があった有機化学1000本ノックのシリーズの続編です。このシリーズの特徴といえば、なんといっても圧倒的問題数。1000題はジョークではありません。本当に1000題あります。問題に1000まで番号が振られています。難易度的にはマクマリー有機化学についている問題よりはやさしいという感じです。とにかく解きまくることが訓練になります。計算ドリルの有機化学バージョンです。
この本は 「ルイス構造式と結合の分極」と名付けられた第0章から始まり、 続く第1-3章の「酸と塩基」、「共鳴」、「結合の生成と切断の基礎」を通して、化学反応の理解の基礎の基礎である化学結合の性質や有機電子論を頭に叩き込まれます。その後は、官能基ごとの反応性の各論にうつります。具体的には、アルケンとアルキンの反応(4-5 章)、芳香族求電子置換反応 (第6章)、ハロゲンの置換/脱離反応 (7-8 章)、アルコールの置換/脱離/酸化反応 (9-10 章)、エーテル、エポキシド、スルフィドの反応(11 章)、カルボニル基の反応 (12-15 章) となっており、大学学部レベルの反応が網羅されています。
本の構成

本書から一部抜粋。注釈は筆者がつけました。
このような書き込み式の形で、たくさん問題が並んでいます。矢印を記入するものだけから、徐々にレベルアップしていきます。
感想
筆者は執筆時点(2021年2月)で学部1年生であり、絶賛有機化学勉強中です。1000 本ノックシリーズは、この記事で紹介している反応機構編だけでなく、前作の命名法編と立体化学編にもお世話になりました。週2時間半程度解いており、命名法編は5週間程度、立体化学編は7週間程度かかって 1000 本 ×2 をやり遂げました。今回紹介している反応機構編は解いている最中ですが、命名法編や立体化学編よりももっと時間がかかりそうです。有機化学1000本ノックはシリーズではありますが、命名法編、立体化学編、反応機構編はそれぞれ独立しています。反応機構編から始めるなどしても問題なく、自分に必要なところをピンポイントで勉強することができます。各章ごとにポイントもついていますが、おすすめは教科書と並行して利用することです。解答もついているので、自習に向いていると思います。
関連記事
関連書籍
参考文献
(トップ画像の表紙写真は化学同人のホームページから引用しました。)