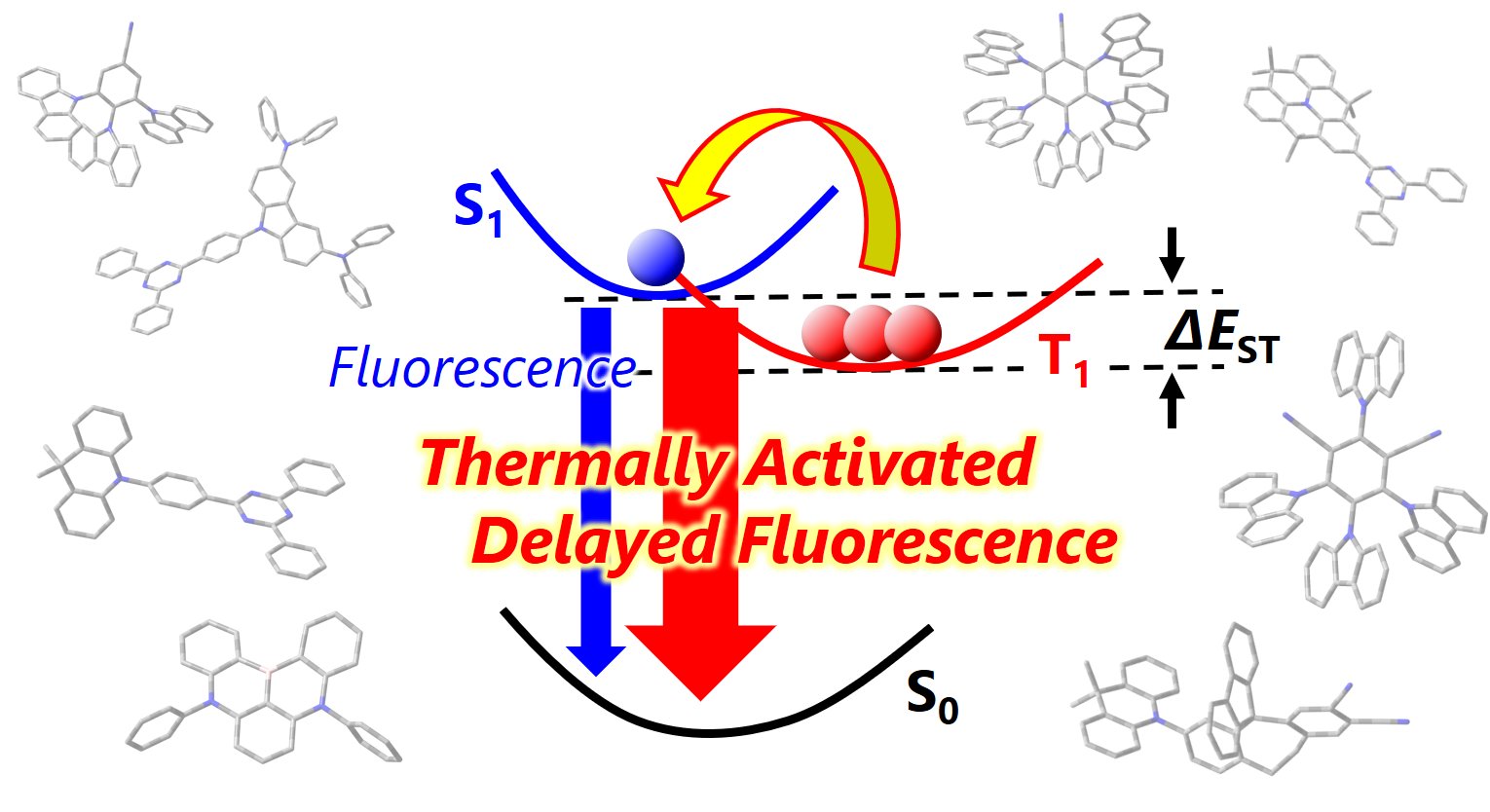研究のデザインから投稿まで、寝る暇も惜しんで書き上げた論文。それが「残念ですが…」という型通りの手紙といっしょに却下されてしまうと、本当にガッカリしますね。
でも、名誉挽回のチャンスはそのときにこそあります。研究自体に欠陥があったのか、それとも発表の仕方に問題があったのか? それがわかれば、次の投稿では採択される可能性を高めることができます。
本コーナーでは、これから論文が却下される10の理由を紹介します。論文の出版をあきらめる前に、もう一度見直してみてください。
*本記事はエナゴ学術英語アカデミーからの寄稿記事に多少の改変を加えたものです
1. ジャーナルの投稿規程を確認しましたか?
論文を投稿する際、ほとんどのジャーナルには独自の(長い)投稿規程があります。
「研究者の名前は論文から削除し、他の紙に書いて添付してください」とか「メールのタイトル欄に研究者の名前を書いてください」など、論文の質にはまったく関係のないルールも少なくありません。しかしながら、これらのルールを守らないと、論文審査以前に却下されることが多々あります。
2. 誤字や脱字はありませんか?

毎日何十もの論文が送られてくる世界的なトップジャーナルの編集長によれば、投稿時の注意点として、「アブストラクト(要約)に一字でも誤字脱字があったら、査読者にまわさないで却下する」とのことです。
誤字脱字は本文だけの問題ではありません。他のジャーナル編集者は「アブストラクトを読む前に表組やグラフを見て、少しでもおかしかったら査読者へまわさない」といいます。
誤字脱字や数字の写し間違いがないか、再度確認しましょう。
3. タイトルに魅力がないのでは?
「読んでみたい!」と思わせるのもタイトルならば、「つまらなそう…」と思わせるのもタイトルです。
「30代日本人男性の…」など読者を限定するようなタイトルでは、国際的なジャーナルの編集者には「読者の多くは興味をもたないのでは?」と思われてしまいます。
また、有名なジャーナルになればなるほど、Impact Factor(掲載される論文が学術界へ及ぼす影響の大きさを示す指数の1つ)を重要視するため、読者を限定するようなタイトルを見た時点で、その論文は「却下」へと一歩近づくことになるでしょう。論文を、自分の研究を世界に売り出す営業マンと考えて、親しみやすくて世界に訴えかけられる、そして英語で響きのいいタイトルを考えてみてください。
4. 統計があればいいというわけではない
専門分野によって差があるとはいえ、昨今、統計的な調査結果を使わない論文は少なくなってきました。
統計的な調査結果がない論文は主観的だと思われる傾向があるからでしょう。しかし、統計的有意差がみられたからといって、論文の信用性が上がるわけではありません。逆に、本当はよい研究でも、不用意な統計の使い方によって信用性を失う場合もあり、それだけの理由で査読者から低い評価を受けることがあります。
統計的な調査結果を使用する場合は、使用の有無だけでなく、たとえば臨床系の研究であれば、被験者数や被験者のグループ分けに適した統計方法などを再検討してみてください。
5. 新しい研究論文が引用されていない
引用されている研究論文がすべて1900年代のものではありませんか?
有名な研究論文は古くなっても引用する価値がありますし、逆に引用しないことで信頼を失う可能性もあります。しかし、引用している研究論文がすべて10年も前のものでは、どんなによい研究でも、「この10年の間に何か重要な発見はなかったのか?」と編集者の不信感を煽ってしまうことになります。
直接関連した内容の論文が出版されていない場合、学会でのパネル発表や博士論文など、出版に至っていない研究でもかまいません。「私はいつもこの研究に関して最先端の情報を集めています」ということをアピールしましょう。
6. 仮説がない
研究者のなかには「仮説を立てること自体が、主観的に研究対象を見ていることになるのでは?」という意見もあります。
しかし現実的には、編集者や査読者は数多くの論文を読まなくてはならないので、一目見ただけで「この人はどうしてこの研究を行ったのか?」がわからなければ、「わかりにくい論文」と考えて、後回し(または却下)することになります。
論文が却下される要因の1つとして、「どうしてこの研究を行ったのか?」と「その仮説を検証するために、この研究デザインがどうして最適なアプローチなのか?」が簡潔にまとめられていないことが考えられます。
この2点を短い文で表現し直してみてください。それぞれを2〜3行でまとめることが望ましいです。
7. 研究結果と研究者の利害関係は?
研究の規模や影響力が大きくなればなるほど、いろいろな所から助成金が集まってきます。
研究者として、主観や私的利益を廃し、限りなく論理的に研究をデザインし、結果を分析するのは当たり前のことです。しかし、たまたまその結果が、助成金を出してくれた会社に好意的な結果となった場合、ジャーナルの編集者や査読者の猜疑心をあおることになります。こうした問題は「助成金を出してくれた団体の会長が、 ある製薬会社の重役も兼任していた」など、助成金にはあまり関係のないところで人脈がつながっている場合でも同じです。
このような場合、論文内で「研究内容とその結果の分析を明確な説明・発表する」こと以外に、「研究の公平性を訴える」ことも重要なポイントとなります。その点を踏まえて、もう一度自分の論文を読み直してみてください。また、第三者に論文を校正してもらう機会がある場合は、事情を説明してから読んでもらうことをおすすめします。
研究者として、自負を持って論理的な研究を心がけている人ほど、このようなことをバカバカしいと思いがちです。
しかし、不必要な疑いを回避するために利害関係を明示しないことは、逆に研究者として自殺行為となりかねます。利害関係はつねに明確に記しておく必要があります。
8. 投稿先のジャーナルの指針と編集委員の趣向
研究者は、最新の論文はいつも敏感にチェックしますが、それを掲載しているジャーナルそのものの目的や経営方針には無頓着になりがちです。しかし、いざ自分の論文を投稿するさいには、このことが重要になってきます。
論文を投稿するさいに「ジャーナルの指針を確認し、それが自分の論文に沿ったものかどうかを確認すること」というのは、よくあるアドバイスの1つです。それでも論文が却下された場合は? 実は、忘れられがちなことの1つに、編集委員たちの存在があります。つまり編集委員が代われば、その編集委員の好みが多少は投稿論文の選択に影響することも否めない、ということです。
査読者からのコメントが届いたら、まずジャーナルの指針とともに編集委員たちの略歴にも目を通しましょう。そうしてからコメントを読むと、査読者の指摘がより明確に理解できるかもしれません。
9. 言いたいことが飛び飛びになっていて読みづらい

著者の言いたいことが飛び飛びに書かれていて、結果として読みにくい文章になってしまうことは、英語が母国語でない私たちにとっては最も厄介な問題です。
日本語と英語では「論理のつなげ方」が違いますので、日本語では筋が通った明確な文章も、英語に直訳すると読みづらく感じられます。これに、略語の多用や、日本の学術界の常識と海外の学術界の常識とのくい違いなどが加わると、説明が必要なことが省略されてしまったり、逆に常識的なことがくどくどと説明されてしまったり、ということが生じます。
査読者から「unclear(不明確)」や「redundant(重複が多い)」というコメントが戻って来たら、英語の論文を書き慣れている人に校正してもらいましょう。
10. 盗用と誤用があった
他の論文の結果や表現を引用する場合は、引用先を明記する必要があります。論文を書いたことのない人にとっては、とても簡単に聞こえるルールですが、実際に論文を書き始めると、このルールには意外にもトリックがあるということがわかります。
たとえば会員限定で発行されているジャーナルに投稿された論文の結果など、引用元の論文全体を自分では確認できないことも多々あるのですが、他の論文でそれが引用されている箇所のみを読んで、全体を読まないまま、「読んだこと」にしてしまうことも技術的には不可能ではありません。しかし、その理解は不十分なままでしょう。
また、いまは多くの論文が電子化されているので、コピー&ペーストによる盗用も簡単にできてしまいます。しかし、引用の盗用や誤用は研究者に取って命取りとなります。掲載前に見つかることは稀ですが、研究者のなかには、不採用の手紙といっしょに査読者から「私はこのようなことは言っていません」と返事が来たという人もいます。掲載後に他の読者から指摘された場合も含め、このようなことがあると、今後、あなたの名前がブラックリストに載る可能性もあります。
他の論文に引用された研究を自分が引用したい場合には必ずオリジナルを確認し、引用するときには細心の注意をもって当たりましょう。どんなに重要な研究でも、確認のできない論文に関しては引用しない、または、脚注にそのことを注記することをお勧めします。
出典元:エナゴ学術英語アカデミー
ケムステ内関連記事
関連書籍
[amazonjs asin=”4422810863″ locale=”JP” title=”最新 英語論文によく使う表現 基本編”][amazonjs asin=”4061531530″ locale=”JP” title=”できる研究者の論文生産術 どうすれば「たくさん」書けるのか (KS科学一般書)”]