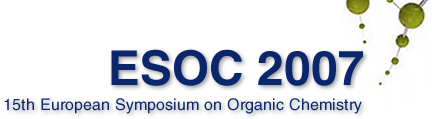概要
ケトキシムのN-O開裂を駆動力としてカチオン性転位を進行させる反応(ベックマン転位)において、オキシムα位置換基がカルボカチオンを安定化させる場合、ニトリルとカルボカチオンを与える開裂反応が競合する。これをベックマン開裂(Beckmann Fragmentation)と呼ぶ。カルボカチオンはE1脱離もしくは求核剤捕捉によって様々な化合物へと変換される。
基本文献
- Beckmann, E. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1886, 19, 988. doi:10.1002/cber.188601901222
- Wallach, O. Justus Liebigs Ann. Chem. 1890, 259, 309. doi:10.1002/jlac.18902590211
- Wallach, O. Justus Liebigs Ann. Chem. 1899, 309, 1. doi:10.1002/jlac.18993090102
- Werner, A.; Piguet, A. Ber. 1904, 37, 4295. doi:10.1002/cber.19040370407
- Werner, A.; Detscheff, T. Ber. 1905, 38, 69. doi:10.1002/cber.19050380109
- Schroeter, G. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1911, 44, 1201. doi:10.1002/cber.19110440205
- Brown, R. F.; van Gulick, N. M. .; Schmid, G. H. J. Am. Chem. Soc. 1955, 77, 1094. doi:10.1021/ja01610a005
- Ferris, A. F. J. Org. Chem. 1960, 25, 12. doi:10.1021/jo01071a003
<Review>
- Grob, C. A.; Schiess, P. W. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1967, 6, 1. doi:10.1002/anie.196700011
- Grob, C. A. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1969, 8, 535. doi:10.1002/anie.196905351
- Gawley, R. E. Org. React. 1988, 35, 14. doi:10.1002/0471264180.or035.01
- Drahl, M. A.; Manpadi, M.; Williams, L. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 11222. doi:10.1002/anie.201209833
開発の経緯
1886年にBeckmann転位の副反応としてはじめて報告され、1890年にO. Wallachによって最適化された条件が報告された。
反応機構
α位が4級炭素・ヘテロ原子(O, S, N)置換の場合には、α-カルボカチオンが安定化されるために、開裂が促進されやすくなる。β位にケイ素やスズが存在する場合にも優先する。転位によって化合物構造に歪みが生じる(熱力学的不利な)場合にも開裂が優先する。
反応例
カルボカチオン中間体の捕捉
三フッ化ジエチルアミノ硫黄(DAST)由来のフッ素アニオンによって捕捉される系[1]。
塩素で捕捉する形式[2]
カルボカチオンを脱離能のあるルイス塩基で捕捉し、引き続く有機金属試薬との反応へと供する系[3]
ケイ素およびスズ配向型形式
βケイ素配向型Beckmann開裂[4]
βスズ配向型Beckmann開裂[5]
全合成への応用
(±)-byssochlamic acidの合成[6]
(+/-)-modhepheneの合成[7]:α位酸素原子が開裂をアシストする。
(−)-elegansidiolの合成[8]
昆虫フェロモンの合成[9] : ケイ素配向型のBeckmann開裂。
関連動画
参考文献
- Kirihara, M.; Niimi, K.; Momose, T. Chem. Commun. 1997, 6, 599. doi:10.1039/a607749h
- Błaszczyk, K.; Koenig, H.; Mel, K.; Paryzek, Z. Tetrahedron 2006, 62, 1069. doi:10.1016/j.tet.2005.11.005
- (a) Fujioka, H.; Matsumoto, N.; Ohta, R.; Yamakawa, M.; Shimizu, N.; Kimura, T.; Murai, K. Tetrahedron Lett. 2015, 56, 2656. doi:10.1016/j.tetlet.2015.03.089 (b) Fujioka, H.; Matsumoto, N.; Kuboki, Y.; Mitsukane, H.; Ohta, R.; Kimura, T.; Murai, K. Chem. Pharm. Bull. 2016, 64, 718. doi:10.1248/cpb.c16-00006
- Nishiyama, H.; Sakuta, K.; Osaka, N.; Arai, H.; Matsumoto, M.; Itoh, K. Tetrahedron 1988, 44, 2413. doi:10.1016/S0040-4020(01)81693-8
- Bakale, R. P.; Scialdone, M. A.; Johnson, C. R. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 6729. doi:10.1021/ja00174a053
- Stork, G.; Tabak, J. M.; Blount, J. F. J. Am. Chem. Soc. 1972, 94, 4735. doi:10.1021/ja00768a055
- Laxmisha, M. S.; Subba Rao, G. S. R. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 3759. doi:10.1016/S0040-4039(00)00486-X
- Cao, L.; Sun, J.; Wang, X.; Zhu, R.; Shi, H.; Hu, Y. Tetrahedron 2007, 63, 5036. doi:10.1016/j.tet.2007.03.123
- Nishiyama, H.; Sakuta, K.; Itoh, K. Tetrahedron Lett. 1984, 25, 223. doi:10.1016/S0040-4039(00)99845-9
関連反応
- グロブ開裂 Grob Fragmentation
- ベックマン転位 Beckmann Rearrangement
- エッシェンモーザー・タナベ開裂 Eschenmoser-Tanabe Fragmentation