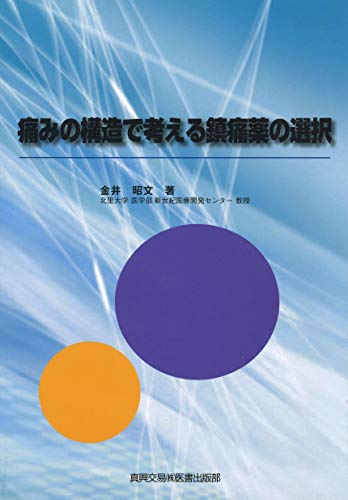アセトアミノフェン (acetaminophen) は、有機化合物の一つ。海外ではパラセタモール (paracetamol) とも呼ばれる。解熱鎮痛剤として古くから使用されている医薬品である。本品単剤を有効成分として含む製品にはカロナール®、タイレノール®、ラックル®速溶錠などがある。その他、数多くの風邪薬や鎮痛用の合剤に含まれている。
構造と化学的性質
4-アミノフェノールのアミノ基をアセチル化したのみの単純な化合物。分子量は 151.165 で、既承認薬の中では小さい方である。
 白色の結晶又は結晶性の粉末である。メタノール又はエタノール (95 )に溶けやすく、水にやや溶けにくく、ジエチルエーテルに極めて溶けにくい。水酸化ナトリウム試液に溶ける (カロナール®錠インタビューフォームより)。
白色の結晶又は結晶性の粉末である。メタノール又はエタノール (95 )に溶けやすく、水にやや溶けにくく、ジエチルエーテルに極めて溶けにくい。水酸化ナトリウム試液に溶ける (カロナール®錠インタビューフォームより)。
合成
古典的には、フェノールのニトロ化と続く接触還元により 4-アミノフェノールを合成し、無水酢酸で N-アセチル化することでアセトアミノフェンが得られる。また、ニトロベンゼンの電解還元により 4-アミノフェノールを得る方法もある。

Scheme 1 古典的なアセトアミノフェンの合成経路
その他に、フェノールの直接的 p-アセチル化とベックマン転位を用いた Celanese 社の経路もある。

Scheme 2 Celanese 社によるアセトアミノフェンの合成経路
効能又は効果
○ 下記の疾患並びに症状の鎮痛
頭痛、耳痛、症候性神経痛、腰痛症、筋肉痛、打撲痛、捻挫痛、月経痛、分娩後痛、がん による疼痛、歯痛、歯科治療後の疼痛、変形性関節症
○ 下記疾患の解熱・鎮痛
急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)
○ 小児科領域における解熱・鎮痛
カロナール®錠インタビューフォームより
歴史
1873 年にドイツの化学者によって初めて合成されたとされる [1]が、英語版ウィキペディアなどによると 1852 年にフランスの化学者によって合成されたとする説もあるようだ。一般用医薬品タイレノールの HP では 1873 年説を採用している。1877 年に解熱鎮痛効果が Joseph von Mering による臨床試験によって見出され、1893年に医薬品としての応用が始まった。しかしその後なかなか普及せず、1948 年に、既に解熱鎮痛薬として知られていたアセトアニリドとフェナセチン (下図) の両者の主要な活性代謝物として認められて以来、解熱鎮痛薬として広く使用されるようになった。

解熱鎮痛薬としての位置付け
19世紀から20世紀中頃まで汎用されていたアミノピリン・アンチピリンなどのピリン系解熱鎮痛薬は、重篤な発疹や血液障害、発がん性などの疑いから1970年代以降徐々に使用されなくなり、代替薬としてアセトアミノフェンの使用が増加した。またアセトアミノフェンと同系統のベンズアニリド構造を有するフェナセチンも腎障害などの副作用のため2000年代からは使用されなくなっている。アスピリンやイブプロフェンといった非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs) と異なり、重篤な副作用であるライ症候群を起こさない。このため、小児のインフルエンザや水痘の解熱など、NSAIDs の使用できない症例の解熱においては第一選択となる。また一般的に NSAIDs の使用が禁忌な15歳未満の小児や妊婦・授乳婦にも使用可能である。子ども用の風邪薬に含まれている解熱成分は主にアセトアミノフェンである。
なお誤解されることが多いが、アセトアミノフェンは NSAIDs には分類されない。NSAIDs の主要な作用機序はシクロオキシゲナーゼ-2 (COX-2) の阻害であるが、アセトアミノフェンは COX-2 をほとんど阻害しない。アセトアミノフェンの解熱鎮痛における作用機序は明確にはわかっていないが、中枢系に作用することが示唆されている。またアセトアミノフェンは COX-2 の阻害が弱いため抗炎症効果はほとんど示さない。NSAIDsは COX のアイソザイムである COX-1 の阻害により消化管粘膜障害作用を示すが、アセトアミノフェンにはそのような効果がなく、比較的消化管にも優しい薬である (ただし、添付文書には「空腹時の服用は避けることが望ましい」とは記載されている)。
代謝と毒性
NSAIDs とは異なる機序でアセトアミノフェンは重篤な毒性を示すことがあるので、過量投与には注意が必要である。アセトアミノフェンは、常用量では大半がグルクロン酸抱合や硫酸抱合によって代謝され排泄される。一部はシトクロムP450 (CYP2E1) で水酸化され、活性代謝物 N-acetyl-p-benzoquinoneimine (NAPQI) を生成する。NAPQI は肝細胞内でグルタチオン(GSH) 抱合を 受けた後、メルカプツール酸誘導体として尿中に排泄される (カロナール®錠インタビューフォームより)。
アセトアミノフェンの大量接種により肝臓での抱合能が飽和・低下すると、CYP2E1 による NAPQI の生成が増加する。いわゆる反応性代謝物である NAPQI は求電子性物質グルタチオンによって解毒されるが、そのグルタチオンも枯渇した場合、蓄積した NAPQI の親電子物質としての毒性 (タンパク質などの生体分子と共有結合する) により重篤な肝障害を発症するおそれがある。また CYP2E1 の誘導剤であるエタノールを多量に摂取すると、グルクロン酸抱合よりも CYP2E1 による代謝が優先し、この場合も NAPQI の生成割合が増加することから、エタノール (酒) とアセトアミノフェンの併用は非常に危険である。

アセトアミノフェンの代謝機構 (こちらの記事より引用)