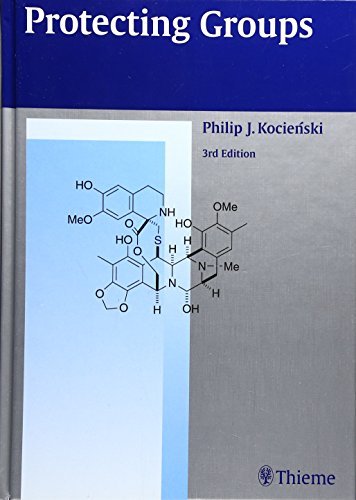概要
カルボニル化合物の保護目的には、アセタールとして保護することが一般的。保護は酸性条件下行われる。還元条件、塩基性条件、求核剤、非酸性酸化剤には安定。
基本文献
・Daignault, R. A.; Eliel, E. L. Org. Synth. 1973, 5, 303.
反応機構
アセタール保護反応は可逆であり、反応を完結させるためにはアルコールを過剰に用いたり、副生する水を除去する工夫が必要となる。

カルボニルの反応性の順列はおよそ以下のとおり。

反応例
Saxitoxinの合成[1]:ハードルイス酸もしくはブレンステッド酸の親和性・活性化能はO>Sである。これを利用すれば、O-アセタールからS-アセタールへと一段階で掛け替えが可能。

野依法[2]:TMSOTfを触媒として、シリルエーテルとカルボニル化合物を反応させると、アセタール・ケタールが高収率で得られる。極低温でも反応が進行する強力な条件。副生するジシロキサン(TMSOTMS)が安定で反応性に乏しいため、逆反応は起こらず、速度論的支配下で保護が行える。

大寺触媒を用いる方法[3]:以下に示すジスタノキサン触媒は強酸に不安定な基質にも用いることができる。穏和なルイス酸としてカルボニルを活性化するとともに、スズアルコキシドを生成し求核能を高めるという共同作用を行っている。また、脱水装置も不要である。

アルデヒド存在下におけるケトンの選択的アセタール化[4]:ジメチルスルフィド-TMSOTfで処理したあとに野依法を行う方法が知られている。

実験手順
エチレングリコールアセタール保護[5]

実験のコツ・テクニック
もっともポピュラーな保護基を以下に挙げる。6員環アセタールは5員環アセタールよりも加水分解速度が速い。

※チオアセタールの脱保護は主に次の3通りが知られる。①メチル化→加水分解 ②酸化(超原子価ヨウ素など)→加水分解 ③水銀(II)による加水分解
参考文献
[1] Tanino, H.; Nakata, T.; Kaneko, T.; Kishi, Y. J. Am. Chem.Soc. 1977, 99, 2818. DOI: 10.1021/ja00450a079
[2] Noyori, R.; Murata, S.; Suzuki, M. Tetrahedron 1981,
37, 3899. doi:10.1016/S0040-4020(01)93263-6 [3] Otera, J.; Dan-oh, N.; Nozaki, H. Tetrahedron 1992,
48, 1449. doi:10.1016/S0040-4020(01)92233-1
[4] Kim, S.; Kim, Y. G.; Kim, D. Tetrahedron Lett. 1992,
33, 2565. doi:10.1016/S0040-4039(00)92243-3
[5] Daignault, R. A.; Eliel, E. L. Org. Synth. 1973,
5, 303.
関連反応
- カルボン酸の保護 Protection of Carboxylic Acid
- 1,2-/1,3-ジオールの保護 Protection of 1,2-/1,3-diol
- アセタール還元によるエーテル合成 Ether Synthesis by Reduction of Acetal
- アシル系保護基 Acyl Protective Group
- アセタール系保護基 Acetal Protective Group
- 1,3-ジチアン 1,3-Dithiane
- スルホン系保護基 Sulfonyl Protective Group
- エーテル系保護基 Ether Protective Group
- カルバメート系保護基 Carbamate Protection
- p-メトキシベンジル保護基 p-Methoxybenzyl (PMB) Protective Group
- ベンジル保護基 Benzyl (Bn) Protective Group
- シリル系保護基 Silyl Protective Group
関連書籍
Greene's Protective Groups in Organic Synthesis
外部リンク
- 保護基(有機って面白いよね!!)
- 保護基(Wikipedia日本)
- Protecting Group(Wikipedia)
- Protecting Group
- Stability of Protecting Group: Hydroxyl (organic-chemistry.org)
- Protecting Group
- ディーン・スターク装置 (Wikipedia日本)
- Dean-Stark Apparatus (Wikipedia)
- アセタール (Wikipedia日本)
- Acetal (Wikipedia)