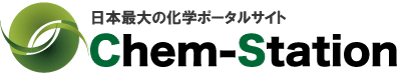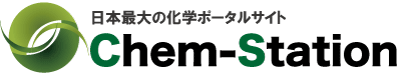空気に不安定な化学物質を扱う「グローブボックス」。筆者は毎日使っています。そんなグローブボックスヘビーユーザーの私が感じた、あるあるをご紹介します。
グローブボックスとは
そもそもグローブボックスとは不活性雰囲気下で化合物を扱える器具のことで、下図のようにボックスの外側にグローブが付いてます。通常内側は、不活性ガス(窒素やアルゴン)で置換してあり一切空気に触れることなく試薬を取り扱うことができます。原料の仕込みから反応、場合によっては溶媒の留去、カラムクロマトグラフィーまでこのグローブボックスの中で行うことができます。ボックス内の水分と酸素量を最小に保つため不活性ガスをフローし続ける場合や水分と酸素を取り除くガス循環清浄システムが取り付けられているものもあります。
また、器具や原料を外からグローブボックス内に入れる場合には、サイドボックスで真空引きと不活性ガス置換を数回繰り返してから本体内部のドアを開けて入れるのが一般的です。高価な機器ですので一人一台というわけにはいかず、数人で共有しているのがどこの研究室でも一般的だと思います。
あるある事例
とても便利なグローブボックスですが、個人的には”いろいろ”と起こりやすい機器であり実例をいくつか紹介します
- いつの間にか試薬やサンプルで溢れている、天秤が汚い、常備品がない
ユーザーが少しづつ物を置いていき、作業スペースが無くなってしまうことが起こります。すると、ただでさえグローブが厚くて作業がしにくいのに、より実験しにくくなり試薬をこぼしたり、ガラスを割ったりすることが多くなります。必要なもの以外は、外で保管すべきです。また、掃除するのが億劫なため、試薬を天秤にこぼしても拭かない人がいるとすぐに汚くなります。さらには、ピペットなどの常に常備品の補充をなかなかしてくれない人もいます。これらの悪いマナーは、最終的には作業効率の低下をもたらします。
- 一人が専有し続けて他の人が使えない
何かと言い訳をつけてグローブボックスを専有し続ける人がいます。グローブボックスは便利ですが、それだけを使って実験するのは、誰でもできます。シュレンクテクニックをうまく併用して実験するが腕の見せどころだと私は思います。
- サイドボックスに入れっぱなし
サイドボックスのガス置換は、時間がかかるため他の作業を同時並行ですることが多いと思います。すると、サイドボックスのことをすっかり忘れてしまう人がいると、グローブボックスの渋滞が起きます。作業をテキパキと終わらせることが化合物にとっても人間関係の雰囲気にとっても重要だと思います。
- サイドボックスでコックが吹っ飛ぶ
サイドボックスでは、内部を効率的にガスで置換するため、真空にします。その際に、サンプル入りのフラスコは、真空が甘いとコックが圧力差に耐え切れず吹っ飛びます。コックが飛ぶとサンプルが飛び出すため、外側のドアを開けると空気と接触してせっかくの実験が水の泡となります。フラスコ内を真空にしていても自身がないときは、ビニールテープ等で固定し安全対策が必要だと思います。
- 状態が悪いと思ったらグローブが破れていた
朝ラボに来たら、何故かボックス内の雰囲気が悪いことがあります。その場合は大抵グローブが破れています。ボックスの中では、鋭利なものはなるべく使いたくないのですが、ハサミやスパチュラ、ピペットは使わざる終えません。その場合には、細心の注意が必要です。なおグローブは高価なので、裂け目が小さい場合には、補修して使っています。
- ロートを入れ忘れて横着し結局こぼす
これは私がよくやる失敗ですが、うっかりロート中に入れ忘れ、溶媒を無理やりフラスコに入れようとしたら盛大にこぼすことがあります。ロートに限った話ではありませんが、ボックスの中に入れ忘れたからといって無理やりやったり、ボックス内の他の物で代用しようとするとろくなことがありません。グローブボックスほど
急がばまわれ=The longest way round is the shortest way home.
(他にもいくつか似たような英語訳があります。)
が重要な器具は無いと思います。
事故や失敗を防ぐために
グローブボックスユーザーの皆様は、共感していただけたでしょうか。新たに使おうと思っている人は、このような失敗があることを肝に命じて欲しいと思います。では、どのように防げばいいのでしょうか。一つは、ユーザーどうしのコミニケーションをよく取るということだと思います。
今終わったよ。あと10分ぐらい掛かるよ。私の実験時間かかるから先使っていいよ。
このような簡単なコミニケーションで、ある研究室では効率が劇的に良くなりました。それと同時に、厳格なルールブックを作成し、それを守ってもらうことも重要だと思います。
関連書籍
関連リンク
- グローブボックス:Wikipedia
- 金井研究室グローブボックスマニュアル:ルールが厳しく決められているようです。
- MBRAUNのウェブサイト:メジャーなグローブボックスメーカー